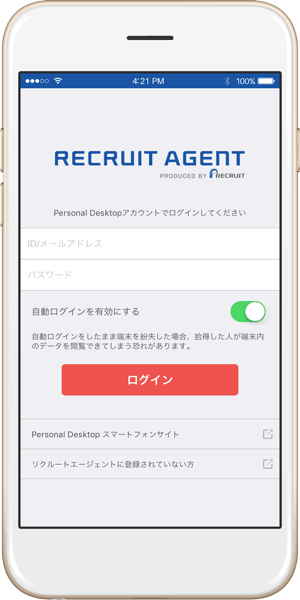転職活動中や内定時、退職時は様々な書類を交わし、入退社に関する手続きが必要となります。転職活動の各フェーズで必要となる書類について、社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所代表の岡 佳伸氏と組織人事コンサルティングSeguros、代表コンサルタントの粟野友樹氏に解説していただきました。
転職活動の開始で必要な書類
転職活動を始める際に必要な代表的な書類は、履歴書と職務経歴書です。書類選考に影響する重要書類なので、書き方例を参考にして準備しましょう。クリエイター系の職種の場合は、履歴書と職務経歴書以外に、過去の作品をまとめたポートフォリオを求められることもあります。
履歴書
履歴書は市販の用紙やテンプレートをダウンロードして作成します。複数の企業に応募する場合は、テンプレートをダウンロードして入力した方が、履歴書作成の手間を減らすことができます。また、履歴書に写真を貼る必要がある場合は、写真スタジオや証明写真機などを利用し、履歴書用の写真を用意しておきましょう。
職務経歴書
職務経歴書は文字数が多いので、パソコンで作成するのが一般的です。時系列に経歴をまとめた「編年体式」、最新の経歴からまとめた「逆編年体式」、キャリアごとにまとめた「キャリア式」の3種類があるので、自身の経歴に合ったテンプレートを選びましょう。
内定時に必要な書類
選考が進み、応募企業から内定が出た場合の必要書類です。内定承諾には期限が設定されているので、書類を受け取ったら期日までに提出しましょう。
内定企業から受け取る書類
受け取る書類
- 内定通知書
- 労働条件通知書
内定が出た場合、企業から内定通知書と労働条件通知書または、内定通知書兼労働条件通知書が送付されます。企業は、採用する人材に対して労働条件を明示する義務があり、以下の1~6(昇給は除く)については、書面を交付して明示しなければなりません。労働条件は非常に重要なので、面接で説明された事項と合致しているか、気になる点がないかをしっかりと確認しましょう。なお、内定通知書は義務づけられていないため、発行するかどうかは企業によって異なります。
書面で明示する項目(昇給は除く)
- 労働契約の期間
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準(更新上限がある場合はその明示)
- 就業の場所及び従事すべき業務および変更の範囲
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等
- 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)、昇給
- 退職(解雇の事由を含む)
出典:よくある質問「採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。」(厚生労働省)
内定企業に提出する書類
提出する書類
- 内定承諾書
内定承諾時に、内定承諾書を交わす企業もあります。企業から内定承諾書が送られてきた場合は、記入日や入社日、氏名などの必要項目を埋めて、設定されている回答期限までに提出しましょう。内定承諾の際に、提出が必要な書類が他にも指定されていることもあります。書類の提出漏れがないように、企業からの指示を確認しておきましょう。
退職時に必要な書類
所属企業を退職する際に必要となる書類です。
所属企業から受け取る書類
退職時に必ず受け取る書類
- 雇用保険被保険者証(企業が保管している場合)
- 年金手帳(企業が保管している場合)
- 離職票
- 源泉徴収票
雇用保険被保険者証と年金手帳は企業が保管していた場合に受け取ります。離職票は、失業保険の申請で必要となる書類です。源泉徴収票は年末調整で必要となるため、入社する企業から提出を求められます。離職票は退職日の翌々日から10日以内に、源泉徴収票は社員の退職後1カ月以内に交付すると決められています。どちらも退職後に会社が手続きする書類なので、届かない場合は請求しましょう。
退職時に必要に応じて受け取る書類
- 退職証明書
転職先に入社するまでブランクがある、転職先が決まっていない場合の、健康保険の切り替え手続きに退職証明書が必要になります。また、転職先企業から提出を求められることもあります。
所属企業に提出する書類
提出する書類など
- 退職届
健康保険被保険者証※2024年12月2日から健康保険被保険者証の新規発行は停止されマイナンバーカード(マイナ保険証)に一体化するため、返納の必要はありません
身分証明書(入館証など)
- 名刺
- パソコン・携帯電話
退職する際は、所属企業のルールに従って退職届などの書類を提出します。健康保険被保険者証は、退職した時点で脱退して転職先の健康保険に新たに加入しますが、有休消化などで最終出社日に直接返却できない場合は、後日郵送で返却するようにします。他にも、通勤定期券や制服、パソコンや携帯電話などの備品や業務で使用していた企画書や顧客リストなどは全て返却しましょう。
なお、退職時のデータの持ち出しは、規約違反にあたることが多く、個人のパソコンに仕事関連のデータが残っている場合は注意が必要です。社内ルールに則り、機密情報に該当するかどうかを上司や人事などに確認した上で対応しましょう。
入社に必要な書類
転職先企業に入社する際に必要となる書類などをご紹介します。
入社企業から受け取る書類
入社企業から受け取る書類など
- 入社手続き案内
- 健康保険被保険者証※2024年12月2日から健康保険被保険者証の新規発行は停止されマイナンバーカード(マイナ保険証)に一体化するため、受け取る必要はありません
- 身分証明書(入館証など)
- 名刺
- パソコン・携帯電話
入社する企業からは、入社手続きに必要な書類の案内が届きます。案内に従って提出書類の準備を進めましょう。業務に必要な入館証や名刺、パソコンなどは入社当日に渡されることが多く、健康保険被保険者証は入社後2週間前後で届くのが一般的です。
入社企業に提出する書類
多くの転職先で提出が必要になる書類
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードの写しで可能)
- 雇用保険被保険者証(被保険者番号のみで手続き可能)
- 源泉徴収票
- 年金手帳・基礎年金番号通知書(マイナンバーで代用可能)
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 給与振込先届出書
社会保険や雇用保険の手続きで、マイナンバーが必要になります。基礎年金番号と連動しているので、マイナンバーカードの写しやマイナンバーの記載がある住民票などを提出することが可能です。扶養控除等(異動)申告書は、扶養家族の有無に関わらず扶養控除、配偶者控除などを受けるために必要です。被扶養者(扶養家族)がいる場合は、健康保険被扶養者(異動)届も必要となり、被扶養者全員のマイナンバーも求められるでしょう。
転職先によっては提出が必要になる書類
- 健康診断書
- 退職証明書
- 入社承諾書・入社誓約書
- 身元保証書
- 免許や資格の証明書
- 卒業証明書
企業によっては、健康診断書や退職証明書、身元保証書や免許や資格の証明書などを求められることもあります。発行までに時間がかかる書類もあるので、指定されたら迅速に対応しておきましょう。
入社まで日数がある、転職先が決まっていない場合の手続き
入社するまでに日数がある、転職先が決まっていない、といった場合は、社会保険や失業保険などの公的手続きを自分で行わなくてはなりません。公的手続きの仕方を解説します。
健康保険の手続き
転職先が決まっていてもいなくても、入社までに日数がある場合は、下記いずれかの方法で健康保険の切り替え手続きが必要になります。
1)国民健康保険に加入する
住所地の各市区町村役所で退職の翌日から14日以内に手続きします。国民健康保険の保険料は住んでいる市区町村によって異なります。また、扶養家族の概念がなく、加入人数によって保険料が決まります。
2)健康保険の「任意継続被保険者」になる
今まで加入していた健康保険の任意継続被保険者として、そのまま加入する方法です。退職の翌日から20日以内に申請書を提出する必要があります。
任意継続被保険者として個人が負担する保険料は、所属企業が負担していた分も支払うため在職時の原則約2倍になります。そのため、退職予定日までに市区町村の窓口と所属企業に保険料を確認し、有利な方法を選ぶと良いでしょう。なお、前職を会社都合や病気で退職し、経済的に保険料の支払いが難しい場合は、保険料の減免措置を受けることも可能です。
国民年金の手続き
20歳以上60歳未満の国民は公的年金制度への加入が義務づけられており、退職して14日以内に、国民年金の第1号被保険者への切り替えが必要です。通常は住所地の役所から自動的に書類が送られてくるので、必定事項を記入のうえ手続きをします。経済的に保険料を支払うのが難しい場合は、市町村役所か年金事務所で免除申請を行うことができ、認められれば保険料の支払いが免除になります。
住民税の手続き
退職後は、毎年6月に住民税の納付書が自宅に郵送で届きます。住民税は、会社員が給与からの天引きで徴収され、会社がまとめて納税する「特別徴収」と、自営業者や退職者などが確定申告をして自分で納税する「普通徴収」の2つの納付方法があります。いずれの方法でも、トータルで納付する金額は同じですが、給与から天引きされる特別徴収の場合は「12分割」、個人で納める普通徴収の場合は「一括」、あるいは退職時期により「2~4分割」となります。
納付書が届いたら、案内に従って支払い回数を選択し、コンビニや金融機関で支払いをしましょう。住民税の税率は、都道府県・市区町村あわせて前年所得の10%が目安です。
失業保険の手続き
転職先が決まっていない場合は、管轄のハローワークで失業保険の手続きをします。退職理由が自己都合/会社都合に関わらず、実際に受給できるまでの期間は最初にハローワークへ行った日が起算日となるので、離職票を受け取ったらすぐに手続きをしましょう。離職票の到着が遅れている場合でも、退職日から所定日数を過ぎれば申請できるので、窓口にその旨を伝えて手続きを進めてください。
なお、転職先が決まっている場合は失業保険の受給資格がないので、入社まで日数があっても手続きは必要ありません。
社会保険労務士法人 岡佳伸事務所 岡 佳伸氏
アパレルメーカー、大手人材派遣会社などでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、雇用保険を活用した人事設計やキャリアコンサルティング、ライフプラン設計などを幅広くサポート。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。
組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルを行っている。
記事更新日:2022年12月20日
記事更新日:2024年10月09日