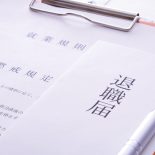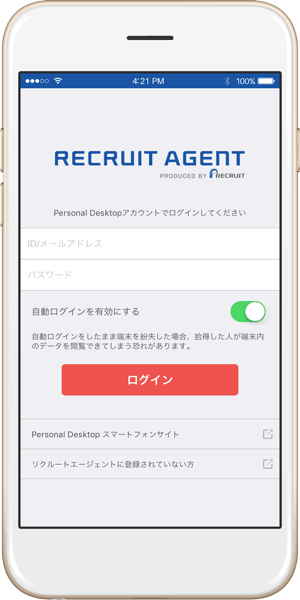退職すると決めたら、まずは会社に退職の意思を伝えなければなりません。しかし、退職の切り出し方について悩んでいる方は多いでしょう。
この記事では「誰に、どのタイミングで、どう切り出せばよいのか」など、円満に退職をするための切り出し方や準備のノウハウを、人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント粟野友樹氏が解説します。
退職の切り出し方
まずは、退職の切り出し方について解説いたします。
退職の意思は直属の上司から伝える
退職の意思は直属の上司から伝えましょう。規模の小さい会社や役職によっては、直属の上司が社長であるということがありますが、この場合は社長に直接伝えても問題ありません。
直属の上司以外である取引先・同僚・先輩・後輩などに退職すると伝えるのは、退職日が正式に決まった後に報告することがおすすめです。不確定な情報が広まる可能性もありますし、上司の立場としては「自分の管轄するチームへの影響を考えて、伝え方を段取りする」ということもあります。また退職交渉を進めていくうちに、現職に留まることになったり、退職日が変更したりする可能性もあるからです。
アポイントをとり2人きりで話ができる場所で切り出す
退職の意思を切り出すときは、相手の都合や予定を確認しましょう。予定を確認するときは、退職の話は伏せ「お話ししたいことがあるので、ご都合のよい時に少しお時間をいただけませんか」と、相手の都合を確認する内容にとどめておくことをおすすめします。退職については対面で理由とともに伝えた方がスムーズだからです。
退職の話を切り出す場所は、相手と二人だけで話ができ、話し声のもれない会議室などを選びましょう。また、相手と二人で食事に行った際や、終業後のお酒の席で退職の話を切り出すのは避けたほうが無難です。退職の話は“交渉”と捉え、冷静に話のできる場を設けるようにしましょう。
遅くとも1カ月前までに伝えるのが一般的
就業規則などに定められた退職までの期間がたとえ短くても、仕事の引き継ぎや有給消化、退職の手続きの時間を考慮すると、希望日の1カ月前までをめどに退職の意思を伝えることが望ましいでしょう。特に、すでに転職先から内定が出ており入社日まで1カ月以内となっている際は、早急に話す場を設けて退職したいという意思を伝えることがおすすめです。
なお、民法上では期間の定めがない雇用契約に関しては、退職を申し入れた2週間後に雇用契約が終了するとされています。しかし、就業規則に具体的な退職までの期間が定められている場合もありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
退職についてどう伝えるべき?
退職交渉がスムーズに進められるような退職の伝え方について解説いたします。
まずは「退職する意思」を丁寧に伝える
退職となると、業務の運営や新しい人材の採用など会社の負担になる可能性があります。そのお詫びの気持ちを込め、退職の話を始める際は「突然で申し訳ございません」と切り出し「退職させていただきたく、今回お時間をいただきました」と伝えましょう。
そのうえで「退職する決心がついている」という意思を丁寧にしっかり伝えます。「退職を考えている」「退職を検討している」「退職の相談なのですが」など、あいまいな伝え方をすると相手は「まだ退職の決心がついていない」と捉え、引き止められる可能性や退職交渉が長引いてしまう恐れがあるので気を付けましょう。
納得してもらえる退職理由を伝える
退職の意思を伝えると、その理由を聞かれることがありますので、あらかじめ退職理由を考えておくことをおすすめします。
「英語のスキルを活かした海外事業に関わる仕事がしたいのですが、今の職場では海外業務がないため、海外事業に関わる経験を積める会社に転職することにいたしました」
「エンドユーザー向けの自社Webサービスを開発できる会社に転職することになりましたので、退職させていただきたいと思います」
現状に対する不満から退職を決意する場合もあると思いますが、円満に退職交渉を進めるうえでは、上記のような「前向き」な理由を説明することをおすすめします。
その際に「今の職場ではその希望は叶えられないので仕方ない」と理解してもらうことが大切です。もちろん、すべて前向きな事情に置き換える必要があるわけではありません。家庭の事情など、理由をそのまま伝えることが必要な場合もあります。
退職の理由を伝える際に注意すること
退職の理由を伝えるときに注意することは次の2点です。
会社への不平不満は避ける
会社側が不満をぶつけられたと感じると心証が悪くなり、円満退職とはいかないことも考えられます。また「不満な点を改善するので、退職はしないでほしい」と引き止めの口実につながる可能性もあります。
一方的に退社日を伝えることは避ける
転職先の企業から内定が出ていて入社日が決定しているときは、その旨を伝えても問題ありませんが、伝え方には注意が必要です。
「実は、次の勤務先から内定をもらい、入社日は〇月〇日で決定しております。急なお願いで大変申し訳ございませんが、引き継ぎをしっかり行ったうえで、〇月末日をもって退社させていただければと思います」など、相手を気遣いつつ可能であれば多少の調整の余地を残したうえで退職日を伝えるとよいでしょう。
「この日までに絶対に退職する」といった一方的な伝え方は避けたほうが無難です。会社側から「自分の都合しか考えていないのか」と思われてしまう可能性もあるからです。
引き止められた場合はどうするか
退職を切り出したときに、現職にとどまってもらうための改善案や今よりも良い条件を提示し、引き止めにあうケースもあるでしょう。しかし、良い条件を提案されたとしても「必ず実現するもの」とは限らないのです。退職の意思が完全に固まっていれば、引き止められたとしても退職するという意思を明確に伝えることがおすすめです。
退職を切り出すときの例文
実際に退職を切り出すときの例文を、ケース別で紹介します。
口頭で直接切り出すときの例文
口頭で切り出すときはその場ですぐに伝えるのではなく、アポイントを取って2人で話せる環境を準備しましょう。
<例文>
「〇〇さん、今後のことでお話ししたいことがあります。〇〇さんのご都合のよろしいときに、2人で話す時間をいただけますでしょうか」
まずは上司から時間をもらい、2人の環境になったときに初めて退職について触れます。
<例文>
「本日はお時間いただきまして、ありがとうございます。突然で申し訳ございませんが、〇〇という理由のため、退職させていただきたく思います。」
納得してもらえる理由を添えて、退職の意思をはっきりと伝えましょう。
メールで退職を切り出すときの例文
上司が忙しくて時間が取れないときでも、メールで退職の意思を伝えるだけにせず、直接会って話をしましょう。アポイントを取ることに関しては、メールでも問題ないでしょう。
<メールでアポイントを取るときの例文>
件名:今後に関するご相談
本文:
〇〇部長
お疲れ様です。
〇〇(氏名)です。
今後のことに関してご相談したい件がございます。
〇〇部長のご都合のよろしいときに、30分ほどお時間をいただくことは可能でしょうか。
直近で私が空いている時間は以下となります。
〇月〇日(月) 12時~17時
〇月〇日(水) 10時~13時
〇月〇日(木) 11時~18時
お忙しいところ恐縮ですが、ご検討のほどよろしくお願いいたします。
(署名)
リモートワーク時の退職の切り出し方
リモートワーク時には、メールやチャットなどの文章で終わりにせず、オンラインツールや対面で退職を伝えましょう。基本的な流れは出社勤務の場合と変わらず、まずは直属の上司にアポイントを取って退職の意思を伝えます。
リモートワーク中は会社に集まる機会が少なく、スケジュールを合わせるのが難しいかもしれません。しかし、メールやチャットで退職を伝えるのは誠意に欠けていると思われる可能性があります。対面が難しければオンラインツールを活用して、お互いに話して退職の意思を伝えることが大切です。
退職の切り出し方の注意点
退職を伝えるときの注意点を3つ紹介します。
メールやチャットだけで終わりにしない
退職の意思を一方的にメールやチャットで送って終わりにしないようにしましょう。このような行為は誠意に欠けていると判断され、円満退職できなくなる恐れがあります。直接退職を伝えるのは言いにくいと感じるかもしれませんが、必ず上司にアポイントを取って退職の意思を伝えましょう。
引き継ぎ期間は必ず考慮する
就業規則に定められた退職の告知から退職日までの期間だけでなく、引き継ぎ期間を考慮して早めに退職日を相談しましょう。例えば就業規則では「1ヵ月前に告知すればよい」となっていても、退職交渉や引継ぎ期間を考慮すると1ヵ月以上かかってしまう可能性があります。
また、社内業務の引き継ぎだけでなく担当顧客がいる場合は、後任の担当者との顔合わせなども考えることが大切です。
繁忙期に配慮する
退職を伝える時期は、繁忙期に配慮することも大切です。繁忙期だと上司のアポイントが取りづらいだけでなく、引き継ぎにかけられる時間も取りづらくなってしまいます。年度末の3月や新入社員が増える4月など、会社によって繁忙期は異なりますが、余裕を持って退職を進められる時期を検討しましょう。
退職にあたり、用意・準備するものは?
退職をするにあたって、事前に用意や準備しておくとよいものを紹介します。
退職願
退職願は上司に退職の意思を伝え、承認された後に提出するのが一般的です。会社によって書式が定められていることがあるので、退職願を書く前に就業規則を確認することをおすすめします。
退職届
退職届は、退職願が受理され正式に退職日が確定した後に提出する書類です。役員や公務員の場合は、退職届ではなく「辞表」として提出します。退職願も退職届も、社内の就業規則に「いつまでに」「誰に」提出するかが決められていたり、雇用形態により提出時期などが異なったりすることもあります。
就業規則の期限を過ぎて提出した場合、提出した書類が受理されず希望の日に退職できないなどの影響も考えられます。事前に就業規則をしっかり確認したうえで、提出の時期やタイミングを検討することをおすすめします。また、提出方法についても規則がある場合もありますので、合わせて確認しておくとよいでしょう。特に提出方法に規定がない場合は、直属の上司や人事部などに提出します。
引き継ぎの流れ・スケジュールを考えておく
円満退職するためには、上司や同僚などにできる限り迷惑をかけずに引き継ぐことが大切です。対応していた業務やプロジェクトの内容・取引先の情報・過去に発生したトラブルとその経緯などを、引継書として分かりやすくまとめます。
また、取引先などへの挨拶周りなども発生することもあるので、どのような形で退職の連絡・後任の紹介などを行うか、上司などと相談しましょう。引き継ぎの期間は、予定外の業務などが発生した場合を考慮し、退社日の数日前にすべて完了するようなスケジュールで設定することをおすすめします。
転職エージェントなら退職時の相談も可能
自分が希望する会社から内定をもらえても、退職交渉がうまく進まないと入社日に退職が間に合わなかったり、退職できなかったりする可能性があります。特に初めての転職となると、スムーズに退職できるのか不安に感じるかもしれません。
転職エージェントを活用すると、退職交渉のコツや進め方なども相談できます。入社日から逆算してスケジュールを決められるので、安心して退職交渉を進められます。少しでも転職活動に関する不安がある方は、転職エージェントの活用も検討してみてください。
組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルを行っている。