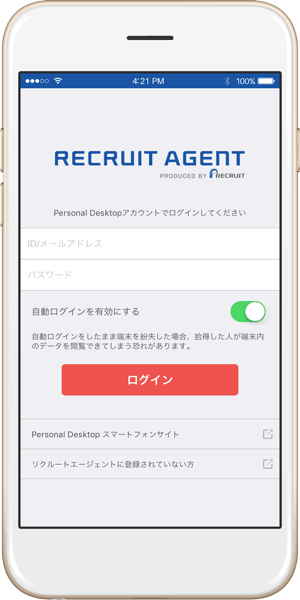「会社を辞めると決意したが、会社には何カ月前に伝えるのが理想的なんだろう」と悩む方もいるでしょう。退職意思を伝える適切な時期、伝え方の注意ポイント、退職までのスケジュール、退職トラブルの防止法などについて、社会保険労務士の岡佳伸氏、組織人事コンサルティングSeguros代表コンサルタントの粟野友樹氏に解説いただきました。
職の意思を伝えるのは何か月前?
まずは、退職意思の表示に関して一般的な常識を知っておきましょう。
就業規則で定められている期間は1カ月が一般的
退職を決意したら、まず所属先企業の「就業規則」を確認しましょう。就業規則には、退職を申し出る期限が記載されています。その規定に従ってください。
退職意思表示の時期は、後任者の選定や業務の引継ぎに要する期間を想定し、設定されています。一般的には、退職意思の表示を「退職希望日の1~3カ月前まで」と定めていることが多いようです。
退職交渉や引継ぎなどに時間がかかる可能性があるなら、早い時期に伝えておくのが望ましいといえます。
法律上は2週間前と定められている
民法上では、期間の定めのない雇用契約の場合、「退職希望日の2週間前まで」に退職届を出せば退職できると定められています。とはいえ、退職後の上司・同僚の負担を少しでも軽減し、円満退社につなげるためには、就業規則で定められた期限を守りましょう。
もし「退職願を出したのに受理してもらえず、強く引き留められる」という状況になった場合は、「2週間で退職」の権利を行使する手段もあります。
退職までのスケジュール目安イメージ
退職意思を表示してから実際に退職するまでのスケジュール感をつかんでおきましょう。もちろん、会社や個人の状況によって異なりますが、おおよその目安期間は以下のとおりです。
社内承認を得る期間「1~2週間程度」
スムーズに承認されるかどうかは、担当業務・ポジション、退職時期の繁忙度合い、後任者の手配の難易度などに左右されます。人手不足の職場、あるいは本人の貢献度が高い場合などは、強く引き留められ、退職交渉が長引く傾向があります。
会社側からの引き留めの手段は多様。昇進・年収アップ・希望部署への異動などを提示されたり、上長や役員クラスと複数回の面談が設けられたりします。
時間がかかる可能性もあることを想定しておきましょう。
業務の引継ぎ期間「1~2週間程度」
引継ぎでは、資料・マニュアルの整理、後任者への説明、後任者を伴っての取引先への挨拶訪問など、ボリュームによっては想定より時間がかかることも多いものです。
後任者がなかなか決まらないと、引継ぎの開始が遅れ、長引く可能性もあります。引継ぎ資料の作成は早めに進めておく、期間に余裕を持たせるなどして、スムーズに引き継げるようにしておきましょう。
上長からの指示や依頼に誠実に対応すると同時に、業務や顧客の整理、優先順位づけなど、どのように引継ぐのか望ましいかを事前に考え、積極的に相談・提案していくことも有効です。
有給休暇の消化期間「+α」
有給休暇の残日数は、転職活動期間や退職交渉開始前後に会社に確認しておくことをお勧めします。制度変更や持越しの上限日数があるなど、有給休暇の残日数に対する認識が異なっている可能性があるからです。
転職に伴う有給休暇の消化期間は、一般的に1~2週間、長くて1カ月程度のケースが多いようです。ただし、有休の消化を優先し、引継ぎをそこそこに休みに入ってしまうと、休暇中や退職後に問い合わせを受けることになるかもしれません。
また、有給休暇消化のために転職先企業への入社日を遅らせると、転職先の採用担当者や配属先の心証が悪くなる恐れがあります。残っている有給休暇はできる限り消化したいものですが、転職先との関係性や要望されている入社日も考慮しながら判断しましょう。
退職までの期間は、可能な限りゆとりを持って
退職までの期間が短い場合、自身が想定したスケジュール通りに進まないこともあります。業務の引継ぎを十分に行わないまま退職すると、残った同僚たちに迷惑がかかってしまう可能性もあります。
退職後も円満な関係を続けるためにも、退職意思表示から退職までの期間は可能な限りゆとりを持たせるといいでしょう。
トラブルを避ける退職の意思の伝え方
退職交渉ではトラブルに発展するケースも見られます。トラブルを防ぐため、退職意思を伝える際に注意すべきポイント、トラブルになりそうな状況での対応策などをお伝えします。
退職意思を伝える際に注意すること
上司に退職意思を伝える際は、メールやチャットツールなどは使わず、対面で伝えます。リモートワークが多い企業であれば、TeamsやZoomなどの対面型のオンライン会議ツールで伝えましょう。これまでの感謝の気持ちを伝えつつ、「○月○日付で退職を希望しております」などと、時期を明示して退職の意を伝えてください。その際、カメラオンにして顔が映らないと対面にはならないので気をつけましょう。
「退職したいと考えています」といった曖昧な表現をすると、「まだ引き留められる」という印象を与え、退職交渉が長引いてしまうかもしれません。
また、退職理由を聞かれても、会社への不満や批判をぶつけないようにしましょう。上司の感情を刺激し、退職までのスケジュールなどについて穏便に話し合えなくなる恐れがあります。転職先企業名を聞かれても、基本的に答える必要はありません。
引継ぎが間に合わない場合
転職先企業が指定する入社日が迫っている、あるいは後任者の手配に時間がかかるなど、退職日までの引継ぎが間に合わないこともあります。
その場合、引継ぐ業務のうち「ストップすると大きなリスクが発生する業務」「リスクの低い業務」に分けてリストを作成し、上司に相談しましょう。
リスクが発生する業務については、チームメンバーや上司など暫定対応する担当者を決めてもらい、マニュアルを作成して引継ぎをします。リスクの低い業務については今後も担当者を置くかどうか上司に判断を仰ぐといいでしょう。
強い引き留めにあった場合
会社側からは昇進・昇給・待遇改善などを提示するほか、希望部署への異動などを提示し引き留めにかかるケースもあります。そこで気持ちが揺らぐこともあるでしょうが、そのときは「そもそもなぜ転職を決意したのか」という目的に立ち返ってみてください。
この先のキャリアプラン、転職によって実現したいことを考え、やはり転職するのがベストと判断したなら、毅然とした態度で意思を示しましょう。
なお、冒頭で触れたとおり、民法上では退職意思を表示後2週間が経過すれば退職することが可能です。会社が退職を承認しなくても、とどまる必要はありません。
退職金・ボーナスの支給はどうなる?
退職金に関する規定は会社によって異なります。一般的には、「定年退職」「会社都合退職」の場合は支給額が高めで、「自己都合退職」の場合は低めに設定されていることが多いでしょう。
多くの会社では国家公務員の規定を参考に「退職手当=基本額(退職日の俸給月額×退職理由別・勤続期間別支給率×調整率)+調整額」(※)の方式で算出します。
通常は勤続期間が長いほど掛け率が高く、就職後1~2年程度で退職する場合は支給しない会社も多数あります。しかしながら退職金の規定は会社によって異なるため、現職の人事に確認できる場合は確認されることをおすすめします。
ボーナスに関しては、退職願・退職届を出す前の期間の実績・仕事ぶりに応じて額が決まるのが一般的です。12月末を退職希望日として11月に退職願を出した場合を例にとると、12月のボーナスは4月~9月を査定期間とすることが多いため、通常の査定基準に沿ったボーナスが支給されます。また、賞与支給日に在籍していないと支給されない企業が一般的です。
(※)出典:退職手当制度の概要(人事院)
社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所代表 岡 佳伸氏

大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会講師および記事執筆、TV出演などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルを行っている。