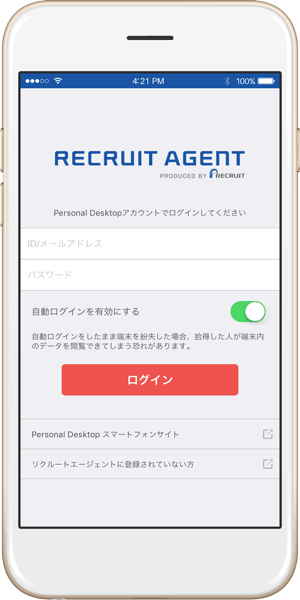退職までのスケジュールを考える際に重要となるのが有給休暇の残日数。できれば、残っている有給休暇はすべて消化してから退職したいものです。そこで、有給休暇に関するルールや、消化するためのポイント、よくある疑問について解説します。
有給休暇とは
一般的に「有給休暇」と呼ばれていますが、正式には「年次有給休暇」という名称が定められています。年次有給休暇の基本となる制度の目的や付与日数、条件や期限について解説します。
年次有給休暇の付与日数
年次有給休暇とは、入社から一定期間勤続した従業員に対して、疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇を指します。有給休暇の名の通り、付与された日数を休んでも給与を減額されることはありません。
付与される条件
有給休暇が付与される条件が2つあります
(1)雇い入れの日から6カ月経過していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
上記2つの条件を満たした場合、10日の年次有給休暇が付与されます。最初に年次有給休暇が付与された日から1年経過し、(2)の条件を満たしていると、11日の年次有給休暇が付与されます。付与される日数は表の通りです。
| 勤続期間 | 休暇日数 |
| 6カ月 | 10日 |
| 1年6カ月 | 11日 |
| 2年6カ月 | 12日 |
| 3年6カ月 | 14日 |
| 4年6カ月 | 16日 |
| 5年6カ月 | 18日 |
| 6年6カ月以上 | 20日 |
年次有給休暇の期限
年次有給休暇は、発生日から2年で消滅することが法で定められています。そのため、長期勤続で有休消化をしなかったとしても、40日以上の年次有給休暇を保有することはできません。
有休消化のタイミング
退職までにまとめて有給休暇を消化したい場合、一般的には2つのタイミングが考えられます。引き継ぎ状況や有給休暇の使い方によってタイミングを考えましょう。
最終出社日の前に消化する
1つは、最終出社日前に有給休暇を取得するケースです。引き継ぎを終えたらいったん有給休暇に入り、退職日に最終出社します。すでに引き継ぎを終えているため、最後の挨拶や荷物の片付けのために出社するケースが多く、貸与されたパソコンや携帯電話、名刺など、会社に返却するものを最終出社日にまとめて返却できる点がメリットです。
最終出社日の後に消化する
もう1つは、最終出社日後に有給休暇を取得するケースです。最終出社日に挨拶をして有休消化に入り、以降は出社することがないため、気持ちの切り替えがしやすくなります。ただし、健康保険証など退職日まで必要となる書類は、退職後に郵送で返却するなどの対応が必要になります。なお、最終出社の挨拶から退職日までに期間が空くことから、パソコンを返却していない場合は、退職を知った人からのメールなどを確認することもできるでしょう。
完全に有休消化するための事前準備
働いて取得した有給休暇。できれば完全に消化して退職したいものです。退職時に完全消化するための事前準備のポイントをまとめました。
有給休暇の日数と有効期限を確認する
退職日までに残されている有給休暇の日数を確認しましょう。
確認の際は、有効期限に注意が必要です。例えば6月30日が退職日で、残り10日間の有給休暇が残っているとします。もし5月31日に期限を迎える有給休暇が含まれている場合は、消滅する5月31日よりも前に消化しなければなりません。期限を迎える有給休暇は先に消化し、残りを退職予定日の直前に充てるなどの工夫が必要になるでしょう。
退職希望日を検討する
有給休暇を完全に消化したい場合は、残っている有給休暇の日数と期限を確認し、引き継ぎ期間と転職先の入社予定日を考慮して退職希望日を設定します。転職先が決まっていない場合は、「残っている有給休暇の日数+引継ぎ期間」で退職日を検討するだけで、完全消化が可能です。ただし、転職先と入社日がすでに決まっている場合は、退職までの日数に限りがあるので有給休暇を消化しきれない可能性があります。また、転職活動中の場合も、有給休暇がたくさん残っていた場合は入社希望日も先になるため、応募先の企業によっては入社希望日の近い他の応募者を優先させる可能性があります。
できるだけ有給休暇を消化するためのポイント
残った有給休暇をできるだけ消化するには、退職までどのように行動すればいいのでしょうか。しっかりと有休消化するためのポイントをご紹介します。
早めに退職を申し出る
早めに退職を申し出て、後任を手配してもらう余裕期間を設けましょう。もし社内に適任者がおらず中途採用する場合は、募集を開始して選考して内定を出して…と、退職を申し出てから後任が入社するまでにどんなに早くても1カ月以上はかかるでしょう。もちろん社内異動であっても、担当している業務を誰かに引き継がなければならないため、やはり1カ月以上はかかります。引き継ぎをしっかりと終えて有休消化に入るために、まず早めに退職を申し出ることにしましょう。
引き継ぎの準備をしておく
まだ内定が出ておらず、退職の申し出ができない場合は、引き継ぎの準備だけでも進めておきましょう。マニュアルを作成しておく、タスクをリストアップしておく、業務整理を行っておくなど、後任が見つかったらすぐに渡せるように、事前にできることがあれば着手しておきます。紙の書類の処分やファイリング、会社に置いてある私物の整理なども少しずつ進めておきましょう。
連休にこだわりすぎない
有給休暇は、できるだけ最終出社日の前後にまとめて取得したいものですが、引き継ぎに無理があるようであれば、“細切れに取る”という選択肢も検討してみましょう。例えば、後任の着任前に1週間取得し、引き継ぎを終えたら残りを取得する、時間単位で取得が可能な職場であれば、毎日半休を取って有給休暇を消化していく、などの方法があります。どうしても消化できなさそうな場合は、引き継ぎ前に有給休暇を取得する、引き継ぎ期間中に時短勤務を試みるなどして柔軟に対応しましょう。
有休が消化できない場合は?有休休暇QA
有給休暇の消化に関する、よくある質問と回答をご紹介します。
有給休暇の取得を認めてもらえない
2019年4月より労働基準法が改正され、企業は年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられるようになりました。そのため、年次有給休暇が10日以上付与されているにもかかわらず取得を認めてもらえないのは、法令違反となります。ただし、企業には「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」という時季変更権があります。著しく業務に差し障りがある時期は避けて、有給休暇のスケジューリングを行いましょう。
消化できなかった有給休暇を買い取ってほしい
有給休暇とは、入社から一定期間勤続した従業員に対して、疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことです。また、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の義務付けがされているように、確実な取得を目的としているものです。そのため、在籍中の有給休暇の買い取りは原則として違法です。ただし、退職して権利を失う有給休暇の買い取りの禁止を法で定めているわけでもないため、企業によっては買い取りをすることもあるようです。どうしても有給休暇が消化できず、買い取りを希望している場合は、まず在籍企業の就業規則を確認し、上司に相談してみましょう。
有休消化中に転職先の企業に入社したい
在籍している企業と、転職先企業の双方に了承を得ることができれば、有給休暇中に働くことは可能です。もし転職先企業の就業規則に、兼業の禁止や届け出が義務付けられている場合は、違反行為となってしまうため就業規則に従うようにしましょう。もし、兼業が可能で双方の企業の了承を得ることができたとしても、雇用保険や健康保険、厚生年金の二重加入はできないので、在籍企業に雇用保険の資格喪失日を転職先企業の入社前日としてもらうか、転職先企業の雇用保険取得日を退職日の翌日に変更してもらう必要があります。また、健康保険や厚生年金も、どちらか一方を選択する手続きをしなければなりません。
後任が見つからず引き継ぎできない
転職先企業が決まっている場合は、上司に入社日が決まっていることや有給休暇を消化したいことを伝え、退職までのスケジュールの相談を。担当業務のうち、取引先への入金や従業員の勤怠管理、プロジェクトのマネジメントなど、遅滞することで経営にリスクを及ぼすような業務がある場合は、優先的にピックアップして、後任が見つかるまでチームメンバーなどに暫定的に対応してもらえないか、上司に交渉します。引き継ぎ事項は一覧にしてマニュアル化するなど、スピーディに引き継げるように準備を整えておきましょう。
入社日を後ろ倒ししたい
どうしても有給消化できないため、「転職先企業の入社日を後ろにずらしたい」と考える方も多いようです。ただし、転職先企業は入社日に向かって、備品やシステム環境などを準備しています。特に欠員募集の採用の場合は、引き継ぎをしたい退職予定者がいるため、入社日を後ろ倒しにすることによって、退職予定者や受け入れる職場に迷惑が掛かってしまいます。入社後に気持ち良く働くために、新しい職場のメンバーに入社前から迷惑をかけるような行為はできるだけ控えておきましょう。
あわせて読みたい参考記事
- 【退職の切り出し方】いつ・どう伝える?注意点や準備することマニュアル
- ケース別退職理由の伝え方│仕事を辞める理由は“前向きさ”が円満退社のカギ
- 辞表と退職願と退職届 それぞれの違いと正しい書き方・渡し方
- 退職のあいさつメールの書き方と例文(宛先別)
社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所代表 岡 佳伸氏
アパレルメーカー、大手人材派遣会社などでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、雇用保険を活用した人事設計やキャリアコンサルティング、ライフプラン設計などを幅広くサポート。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。