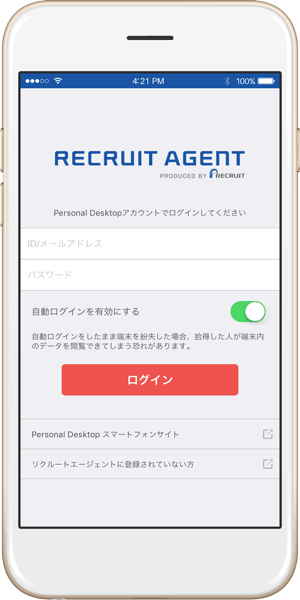職場や立場によって仕事の忙しさや業務量、プレッシャーなどは異なるものです。「会社に疲れた」と感じる場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。そこで今回は、会社や仕事に疲れてしまう原因や、つらい状況を改善し休養を取るための方法などについて、組織人事コンサルティングSeguros、代表コンサルタントの粟野友樹氏と、社会保険労務士の岡佳伸氏がアドバイスします。
目次
「会社に疲れてしまった」と感じたら?
「会社に疲れた」「前向きに仕事ができない」と感じる場合は、まず自分の状態を冷静に把握してはいかがでしょうか。厚生労働省は、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を開設しています。所要時間約5分で疲労蓄積度をチェックできるので、自分の疲労蓄積度を診断してみましょう。
(※)出典:厚生労働省「こころの耳」
働く人の疲労蓄積度セルフチェック(働く人用)
ビジネスパーソンが会社に疲れる主な原因とは?
現代は、多くのビジネスパーソンが会社や仕事に疲れたり、ストレスを感じたりしています。
厚生労働省の調査(※)によると、働く人の82.7%が、仕事や職業生活に関して強い不安や悩み、ストレスを感じていることが分かっています。
ストレスの主な内容については、「仕事の失敗、責任の発生等」が39.7%と最も多く、次いで「仕事の量」39.4%、「対人関係(セクハラ・パワハラを含む)」29.6%、「仕事の質」27.3%、「顧客、取引先からのクレーム」26.6%となっています。
(※)出典:「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)【個人調査】」(厚生労働省)
自分が会社に疲れている理由を確認しよう
疲労蓄積度や、多くの人が仕事に疲れる原因を確認したら、次に、自分が「疲れた」と感じる理由をさらに深掘りしてみましょう。同じ状況でも、感じ方、捉え方は人によって違うことが多々あります。自分自身に向き合い、理由を探ることで、解消する対策を講じられるかもしれません。以下によくある理由を紹介します。
過剰な業務量や残業量
労働時間が長いため、肉体的な疲労が溜まって回復しにくくなっているケースです。人手不足、業務量過多、責任感が強いなどの理由から、休みたくても休めずに疲れが蓄積していることがあります。
労働基準法では、時間外労働(休日労働を含まず)の上限は、原則として月に45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります 。自分が過度の残業を続けていないか、勤務時間を確認してみましょう。
人間関係のストレス
人間関係がうまくいかないと、ストレスから精神的な疲れが溜まることがあります。職場で仕事をする上では、苦手な相手であっても避けて通ることはできず、「毎日話すだけで疲れる」とぐったりしている人もいるでしょう。その場合、休息を取るだけでは根本的な解決にはならないかもしれません。
仕事の成果が出ない・評価されない
「頑張っているのに評価されない」といった、上司や会社への不満も、疲れる理由になることがあります。例えば、数字に表れる結果しか見てもらえず、プロセスでの努力や工夫が報われない場合などは、徒労感が疲労として蓄積する可能性もあります。会社に行くのが億劫になる、仕事に集中できなくなるなど、モチベーションが低下してしまうこともあるでしょう。
仕事を自分でコントロールできない
業務を進めるに当たってあまりに裁量権がなく、自分で自分の仕事がコントロールできない状況下では、ストレスを溜め込んでしまう可能性があります。日常的に突発的なタスクが多いため効率が悪かったり、頼まれた仕事を断り切れずに抱え込んだりしている場合も、精神的な負荷が高く、疲労を感じてしまうことがあるでしょう。
周りのサポートが受けられない
「ドライな職場で助け合いの文化がない」「経験が少ないにもかかわらず、難易度の高い仕事でも周囲がフォローしてくれない」といったことも、精神的に疲れる理由になる可能性があります。先輩や上司からのサポートが得られにくい環境では、不安感や孤立感を覚えやすくなり、仕事の負荷を強く感じてしまうでしょう。
与えられた仕事が合わない、やりがいがない
自分に合わない仕事を続けるのは、思いのほかストレスになるものです。特に、したくない仕事を会社から指示されて、不本意な気持ちのまま仕事を続けていると、モチベーションの維持が難しくなります。仕事に向き合う意欲が出ず、疲弊感が蓄積してしまうでしょう。
会社に疲れたときに試したい対処法
会社や仕事に疲れたと感じたら、まず意識して休みを取り、心身ともにリフレッシュすることが重要です。週末は思い切り趣味を楽しむなど、気持ちを切り替えて仕事のことを忘れる時間を作りましょう。
同時に、自分が会社に疲れてしまう根本的な原因を軽減・解消する策を講じることも大切です。ここでは、対処法の例をご紹介しましょう。
仕事の進め方・業務フローを見直す
業務量の多さが負担になっている場合は、仕事の進め方を見直すことが大切です。現状の業務フローを洗い出して、「本当に必要な作業は何か」を考えて優先順位を整理しましょう。中には、過去の慣習で残されているだけだったり、ニーズは低いのにルーティンワークになっていたりする業務もあるかもしれません。客観的な視点を持って、業務の効率化を図っていきましょう。
苦手な相手からはなるべく距離を置く
人間関係で疲れる場合は、その人から物理的に距離を置くのも一案です。例えば、苦手な相手とやりとりをする際は、メールやチャットなど対面以外の方法を使うことなどが挙げられます。根本的な解決にはなりませんが、ひとまず接触を減らすことでストレスを感じる時間を減らしましょう。
なお、コミュニケーションに支障が生じることで、仕事の進捗自体に影響が出てしまう場合は、上司や人事部などに相談して配置換えなどを検討するのも一つの方法でしょう。
評価や業務量について上司と相談する
仕事が評価されず徒労感を覚えている場合は、敢えて自分から行動してはいかがでしょうか。例えば、「こんな工夫をしてみました」「この仕事について反響はどうでしょう?」などと、上司に直接フィードバックをもらいに行くことも一案です。
自身の仕事の評価を改めて知ることで、日々の業務に意味を感じることができ、意慾が高まる可能性があります。また、任されている業務量のバランスが悪く、負担を感じている場合は、担当業務に関する相談をするのもお勧めです。一人で抱え込まず、チーム全体で課題をシェアすることで、問題が解決できるかもしれません。
SOSを出して周囲の人を巻き込む
ひとりで仕事や問題を抱え込み、ストレスを溜めているだけで、周囲の人は全く気づいていない可能性もあります。裏を返すと、自分からSOSを発信すれば、すぐに対処してもらえるかもしれません。「この仕事のここが難しいので誰か教えてほしい」「キャパオーバーなのでサポートが欲しい」などと周囲の人に相談して、解決策を探ってみると良いでしょう。
異動を検討する
やりがいを感じない、裁量権がないといった状況がストレスや疲れにつながっているとしたら、同じ部署ですぐに状況を変えることは難しいかもしれません。この場合は、自分が望む仕事や、自律性の高い働き方を実現できる部署への異動や、プロジェクトに参加できる方法などを探してみましょう。社内の制度を調べてみるだけでも、将来の仕事への期待値が高まり、モチベーションが上がるかもしれません。
家族や友人・知人と対話してみる
厚生労働省の調査(※)では、仕事のストレスを相談できる人として「家族・友人」を挙げた人が71.7%に上ります。社内に相談相手を持つことも大切ですが、難しい場合は、家族や友人・知人など、社外の人に話を聞いてもらうのもお勧めです。
ネガティブな感情を口にするだけでも苦痛が緩和され、心の疲れが改善されることもあります。職場や仕事内容を知らない相手でも、悩みを打ち明けるうちに思考が整理され、解決策が見つかる可能性があります。
(※)出典:「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)【個人調査】」(厚生労働省)
社内外の専門家に相談する
問題を自分だけで解決しようとせず、専門家に相談して話を聞いてもらうことも一つの方法です。所属企業に産業医やメンタルヘルスの問い合わせ窓口が設置されている場合は、連絡して状況を説明してみましょう。もし所属企業に適切な窓口がない場合は、前述の厚生労働省のポータルサイトに働く人向けの相談窓口やQ&Aなどが掲載されています。
(※)参考:厚生労働省「こころの耳」
疲れの原因は、実は会社ではなくプライベートな原因の可能性もある
自分では「会社に疲れた」と思っていても、実はプライベートな理由や体調面に根本的な原因があることもあります。例えば、友人関係や恋愛関係、家族関係における悩みや、介護・育児・家事などで疲れが溜まっていたり、介護・出産・結婚などのライフステージの変化によるストレスを感じていたりするなどです。また、食事・運動・睡眠などの生活習慣に課題があり、慢性的な体調不良が原因となっていることもあるでしょう。
悩みを人に相談してみたり、家族にサポートを頼んだり、生活習慣を見直して、健康的な食事や十分な睡眠によって体調を整えるだけでも、仕事が楽しくなり、モチベーションが戻ってくる可能性があります。
会社に疲れたという気持ちが改善できなければ「まとめて休む」ことも考えよう
色々な対処方法を試みても疲れが軽減しない場合は、ストレスの源である会社や仕事から物理的に距離を取ることも一つの方法です。できれば数日以上仕事から完全に離れて、しっかり心身を休めましょう。
有給や特別休暇を利用する
年間休日とは別にまとまった休みを取得するには、年次有給休暇のほか、制度があれば「リフレッシュ休暇」などの特別休暇を利用する方法があります。
2018年より、年に10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、年5日の有給休暇の取得が義務づけられています。職場に遠慮して「休みにくい」という人もいるかもしれませんが、法律で義務づけられている休暇なので、遠慮なく取得しましょう。例えば、金曜日と月曜日に有給休暇を取り、週末をはさんで4連休にする方法もあります。お盆や年末年始の季節休暇以外に4日間まとめて休むことは特別感があり、良い気分転換になるでしょう。
一定期間休職する
休んでも一向に疲れが回復せず、不眠や食欲不振などもある場合は、心身に不調をきたしている可能性もあります。深刻な状況になる前に、周囲と相談の上、一定期間休職することも検討しましょう。責任感の強い人ほど休むことに躊躇したり、不安になったりする傾向がありますが、仕事を続けるには、心身を休めて回復してから復帰するのが良いでしょう。
休職制度について
企業の休職制度の中で、一般的に病気やケガで就業できない場合に利用できるのが傷病休職です。法的な義務はないため、制度の有無や休職できる期間などは企業によってさまざまですが、制度を設ける場合は必ず就業規則などに規定を記載することになっています。
まず主治医の診断を受け、就業規則を確認の上、休職の必要性とその理由を、上司を通じて会社に申請します。最初に休職を申し出る時点で、医師の診断書が求められることが多いようです。さらに必要に応じて面談が行われ、休職期間や復職の見込み、休職中の待遇などを確認した上で、申請が承認されます。休職期間は「勤続3年未満は最長○カ月、3年以上は○カ月」などと、就業規則で定められていることが一般的です。復職は、主治医及び会社と相談の上で進めていくことになります。
休職中の給与や手当、社会保険などについて
休職期間中は、多くの企業で給与が支払われませんが(賞与は評価期間に応じて支給されるケースも)、業務外の病気やケガ、メンタルヘルス不調で仕事を休んだ場合は、加入している健康保険から傷病手当金を受けることができます。申請には加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)所定の傷病手当金支給申請書に会社による給与支払い状況の証明、主治医の証明などが必要で、基本的に労働者本人が手続きを行います。
なお、休職期間中であっても、厚生年金保険料と健康保険料の本人負担分、新卒2年目以上の人は住民税も支払う必要があることは知っておきましょう。
避けたいのは、心身の不調で働くのがつらくなり、医療にもかからずそのまま退職してしまうことです。在職中に医師の診断を受けなければ、傷病手当金は受けられません。また、失業保険の基本手当を受給するには、すぐに働ける状態であることが条件となります(※)。受給中は何らかの就職活動を行い、定期的にハローワークに報告する必要があります。そのため、不調で働けない状態が続けば、失業保険も受給できなくなってしまいます。勤務先に制度が整備されていなくても、まずは医師の診察を受けて、会社に相談してみることをお勧めします。
(※)出典:「基本手当について」(厚生労働省)
なお、社内で休職の相談がしづらい場合は、下記のような公的に設置された窓口に相談しても良いでしょう。
(※)参考:厚生労働省「総合労働相談コーナー」
(※)参考:厚生労働省「こころの耳「相談窓口案内」」
転職活動で視野を広げるのも一つの方法
会社や仕事に疲れを感じて、解決を試みても状況が改善しない場合は、「転職する」という選択肢もあります。まずは心身を休めて、時間や気持ちに少し余裕ができたら、情報収集や転職活動を始めてみても良いかもしれません。
例えば転職エージェントを利用すると、転職支援のプロであるキャリアアドバイザーにキャリア相談をすることもできます。客観的なアドバイスを受けることで、自分の新たな可能性を知ったり、今の会社の良さを再認識したりすることもできるでしょう。
さまざまな企業や業界・職種の働き方を知ることにより、現在置かれている状況を客観的に判断することができます。また、転職活動で色々な企業の話を聞いてみることで、視野を広げることもできます。もし「現職以外にも選択肢がある」ということを知れば、それだけで将来に希望が持てて、会社に疲れる状況も改善されるかもしれません。
疲れている状態のときは、どんどん視野が狭くなってしまう傾向があります。十分な休息を取ってから、情報収集や転職活動を進めて視野を広げ、今後のキャリアを冷静に判断すると良いでしょう。
社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所代表 岡 佳伸氏
大手人材派遣会社にて1万人規模の派遣社員給与計算及び社会保険手続きに携わる。自動車部品メーカーなどで総務人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険適用、給付の窓口業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として複数の顧問先の給与計算及び社会保険手続きの事務を担当。各種実務講演会講師および社会保険・労務関連記事執筆・監修、TV出演、新聞記事取材などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。
記事更新日:2024年09月19日
記事更新日:2025年06月03日 リクルートエージェント編集部
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。