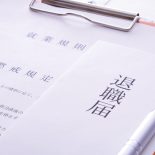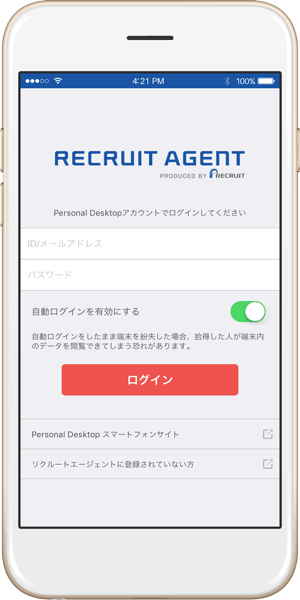所属企業を退職する際、「残っている有給休暇を全て消化して辞めたい」と考える人も多いようです。有給休暇の基本的なルール、有給休暇を完全に消化する方法、有休消化のタイミング、有休消化できない場合の対処法、注意点などについて、社会保険労務士法人 岡 佳伸氏と組織人事コンサルティングSeguros、代表コンサルタントの粟野友樹氏が解説します。
有給休暇とは
有給休暇は、正式には「年次有給休暇」という名称が定められています。年次有給休暇の基本となる制度の目的や付与日数、条件や期限について解説します。
有給休暇のルール
年次有給休暇とは、入社から一定期間勤続した従業員に対して、疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇制度です。有給休暇の名称の通り、付与された日数は会社を休んでも給与を減額されることはありません。
年次有給休暇は、「1.入社から6カ月が経過していること」「2.その期間の全労働日の8割以上出勤していること」の2つの要件をクリアした場合に、10日の年次有給休暇が付与されます。
また、最初に付与された日から1年経過し、最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出勤していれば、11日の年次有給休暇が付与されます。その後同様に要件を満たすことにより、次の表に示す日数が付与されます。
有給休暇の付与日数
| 勤続期間 | 休暇日数 |
| 6カ月 | 10日 |
| 1年6カ月 | 11日 |
| 2年6カ月 | 12日 |
| 3年6カ月 | 14日 |
| 4年6カ月 | 16日 |
| 5年6カ月 | 18日 |
| 6年6カ月以上 | 20日 |
有給休暇の期限
年次有給休暇は、発生日から2年で消滅することが労働基準法で定められています。そのため、長期勤続で有休消化をしなかったとしても、40日以上の年次有給休暇を保有することはできません。
有休消化の「年5日の取得義務」とは?
労働基準法の改正により、2019年4月から全ての企業において、年5日の年次有給休暇を従業員に取得させることが義務づけられました。対象者は「法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者」であり、管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
年次有給休暇が付与された人は、付与された日から1年以内に5日消化する必要があります。
有給休暇を完全に消化する方法
退職までに有給休暇を完全に消化したい場合は、事前の準備やスケジューリングが重要になります。完全に消化するためのポイントを6つご紹介します。
就業規則を確認する
退職するにあたり、確認しておきたいのが就業規則です。「希望日の○日前までに退職を申し出ること」など、退職の申し出の期限を設けているケースがあります。退職希望日が就業規則に定めている退職の申し出期間に間に合っているかを確認しておきましょう。また、就業規則の有給休暇についての規定も確認しておくと安心です。
有給休暇の日数を正しく把握する
就業規則を確認したら、残っている有給休暇の日数を正しく把握します。給与明細や勤怠システムに明示する企業もありますが、有給休暇の残日数の通知に法的な義務はありません。明示していない場合は、自分で計算するか人事に確認してみましょう。
また、有給休暇の有効期限に注意が必要です。例えば、6月30日が退職日で、残り10日間の有給休暇が残っているとします。もし5月31日に期限を迎える有給休暇が含まれている場合は、消滅する5月31日よりも前に消化しなければなりません。期限を迎える有給休暇は先に消化し、残りを退職予定日の直前に充てるなどの工夫が必要になるでしょう。
退職スケジュールを立てる
有給休暇の残日数を把握できたら、退職までのスケジュールを立てます。退職希望日から逆算して有給休暇を設定し、その前が引き継ぎ期間になりますが、転職先の入社日が決まっていて退職までの日数に限りがある場合、有休消化しきれない可能性があります。一般的に、転職先企業は入社日に向けて受け入れ体制を整えるため、有休消化のために入社日を延長してもらうことは難しいでしょう。
早めに退職を申し出る
退職希望日までに必要な日数があったとしても、実際に退職を申し出たら想定外の状況になることもあるものです。「辞められては困る」「後任が見つからない」などの理由で強く引き留められる、考えていたよりも引き継ぎに時間がかかる、などの事態も考えられます。有給休暇を完全に消化するために、退職を申し出るタイミングから退職希望日までの期間には十分な余裕を持つことが重要です。
引き継ぎ準備をしておく
後任が見つかる前に、できるところから引き継ぎの準備をしておくことも有効です。例えば、業務・顧客の一覧やマニュアルの作成、ファイルや資料などの置き場を整理するなど、退職を申し出て後任が決まったら、すぐに引き継ぎを始められる準備をしておくと良いでしょう。また、引き継ぎの準備をしておくことで、引き継ぎ期間の目安を掴めるというメリットもあります。
連休にこだわりすぎない
退職予定日までにまとめて有休消化できるのが理想的ですが、難しいようであれば細切れで有休消化していくという方法もあります。
例えば、後任の着任前に一部を取得しておき、後任が着任して引き継ぎを終えたら残りを取得しても良いでしょう。半日単位・時間単位で取得できる制度が設けられていれば、半休や時間休を活用し、引き継ぎを進めながら少しずつ消化していけるでしょう。
退職で有休消化するタイミングは?
有休消化するタイミングとして、「最終出社日の前」と「最終出社日の後」の2パターンがあります。それぞれの活用法の一例を挙げてみましょう。
最終出社日の前に有休消化する
最終出社日の前に有休消化する場合、業務の引き継ぎや取引先への挨拶などを終えた後で有給休暇を取得します。そして、退職の期日に最終出社して社内関係者への挨拶、貸与されていた備品や名刺などの返却、私物の回収などをするのが一般的です。
最終出社日の後に有休消化する
最終出社日後に有給休暇を取得する場合、最終出社日に挨拶を済ませて有休消化に入り、有給休暇の終了と同時に退職します。転職に際して遠方に転居する場合、次の会社へ早く気持ちを切り替えたい場合には、このタイミングが適しているといえるでしょう。
有休消化できない場合の対処法
退職予定日までに有休消化できない場合の対処法について、2つのパターンをご紹介します。
在籍企業の退職予定日を延長してもらう
転職先が未定、あるいは転職先企業への入社日までに余裕がある場合、在籍企業に相談して退職予定日の延長を打診してみましょう。退職予定日を変更できなかったり、転職先企業への入社日が迫っていたりする場合は、引き継ぎ期間を短縮できないか交渉してみる方法もあります。
なお、在籍中に有給休暇を買い取ってもらうことは、原則として違法となります。有給休暇とは、入社から一定期間勤続した従業員に対して、疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇です。「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の義務づけがされているように、確実な取得を目的としています。
ただ、退職のために権利を失う有給休暇の買い取りまでは禁止されていないため、中には買い取りに応じる会社もあるようです。とは言え、「買い取りしてくれるか」「いくらで買い取ってくれるか」はあくまでケースバイケースです。人事や労務部門に相談してみましょう。
転職先企業の入社日をずらしてもらう
転職先企業に相談し、入社日を後ろにずらせるかどうかを確認する方法もあります。ただし、転職先企業側は入社者を受け入れるために、人員体制や環境などを準備しています。特に欠員募集の採用の場合は、引き継ぎをしたい退職予定者がいるため、入社日を後ろ倒しにすることによって、受け入れる職場に迷惑がかかってしまいます。転職先企業への相談は、どうしても有休消化したい場合の最終手段としましょう。
在籍企業と転職先企業に相談して有給休暇中に入社する
在籍企業と転職先企業の双方と相談し、了承を得られれば「有給休暇中に転職先企業に入社する」という方法も考えられます。いずれの企業でも副業・兼業を禁止していなければ、有給休暇中に働くことは可能です。
ただし、雇用保険や健康保険、厚生年金の二重加入はできないので、在籍企業に雇用保険の資格喪失日を転職先企業の入社前日としてもらうか、転職先企業の雇用保険取得日を退職日の翌日に変更してもらう必要があります。また、健康保険や厚生年金も、どちらか一方を選択する手続きをしなければなりません。
完全に有休消化する場合の注意点
せっかく付与されている有給休暇を完全に消化したいと思うのはもっともなのですが、有休消化にこだわり過ぎると、転職のチャンスを逃してしまう可能性もあります。例えば、有休消化を前提に、応募先企業に希望入社日を伝えることで、「そのタイミングの入社ではプロジェクト始動に間に合わない」などと、採用を見送られてしまう可能性も考えられるでしょう。
今後のキャリア構築を考えれば、有休消化よりも適切なタイミングでの入社を優先した方が良いケースもあるため、長期的視点を大切にして行動を選択しましょう。
また、有休消化を優先して引き継ぎをおろそかにすると、上司や同僚の心証を損ねるかもしれません。退職後も良好な人間関係を保っていきたいのであれば、引き継ぎもしっかりと行いましょう。
有休消化に関するQ&A
有休消化に関する、よくある質問にお答えします。
Q.有給休暇の取得を認めてもらえない場合は?
前述の通り、年次有給休暇が10日以上付与される従業員に対して、年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務づけられています。また、付与された年次有給休暇は本来、全て取得されるべきものです。そのため、年次有給休暇が付与されているにもかかわらず取得を認めてもらえないのは、法令違反となります。ただし、企業には「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」という時季変更権があります。著しく業務に差し障りがある時季は避けて、有給休暇のスケジューリングを行いましょう。
Q.後任が見つからず引き継ぎできない場合は?
転職先企業が決まっている場合は、上司に入社日が決まっていることや有休消化したいことを伝え、退職までのスケジュールを相談しましょう。担当業務のうち、取引先への入金や従業員の勤怠管理、プロジェクトのマネジメントなど、遅滞することで経営にリスクを及ぼすような業務がある場合は、優先的にピックアップして、後任が見つかるまでチームメンバーなどに暫定的に対応してもらえないか、上司に交渉します。引き継ぎ事項は一覧にしてマニュアル化するなど、スピーディに引き継げるように準備を整えておきましょう。
社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所代表 岡 佳伸氏
大手人材派遣会社にて1万人規模の派遣社員給与計算及び社会保険手続きに携わる。自動車部品メーカーなどで総務人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険適用、給付の窓口業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として複数の顧問先の給与計算及び社会保険手続きの事務を担当。各種実務講演会講師および社会保険・労務関連記事執筆・監修、TV出演、新聞記事取材などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。
記事更新日:2024年09月10日
記事更新日:2025年09月18日
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。